| 休憩の後は、見沼観察会でその単純にして複雑な生活史がたいへんおもしろかったという声の多かったアブラムシの講習会です。アブラムシのいろいろな話があった中から2,3紹介しましょう。 |
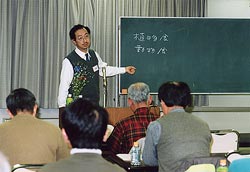 講演中の松本先生 講演中の松本先生 |
|
| ●セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ |
| 1990年代初頭、千葉県立中央博物館からの問い合わせで調べてみると、セイタカアワダチソウに日本国内では見つかっていないアブラムシがいることがわかりました。セイタカアワダチソウは北アメリカ原産の植物ですが,原産地では数種類のアブラムシが寄生していることが報告されていて、その中のどれか、または新種なのか論議されました。最終的に精査の結果、原産地のセイタカアワダチソウに見られるアブラムシと同一種ということがわかり、日本新記録のアブラムシとなったわけです。その後、調査をした結果、鹿児島県から福島県まで広く分布していることがわかりました。いわゆる侵入種ですが、おそらく戦後、セイタカアワダチソウについて国内に入ってきたものと思われます。和名がついてなかったのでセイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシとしました。アブラムシの和名は、寄主植物名に続けて、形態的特徴そして最後にアブラムシと続けることが一般的です。そのため、セイタカアワダチソウヒゲナガブラムシのように長い和名がついてしまうのです。 |
|
 |
| セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシの無翅型 |
|
 |
 |
| 産子中のセイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ有翅型 |
|
|
| ●アリと一緒 |
| アブラムシを別名でアリマキもと言います。漢字では蟻の牧、つまりのアリの牧場という意味です。アリがアブラムシの出す甘露を占有するために、アブラムシを飼っているように見えたのでしょう。クチナガオオアブラムシの仲間は特に長い口吻(こうふん)を寄主植物に差しこんでいるため、天敵からうまく逃れることはできません。しかし、アリがいると天敵が寄ってきません。つまりアリはアブラムシのボディガードとして働いていることになります。しかし、種によっては、アリが甘露を出さなくなったアブラムシやアブラムシが増えすぎると、アリがアブラムシを食べてしまう例も見つかっています。自然の出来事はそう単純ではないようです。 |
 |
| ヨモギヒゲナガアブラムシとトビイロケアリ |
|
 |
 |
| イチゴネアブラムシから甘露をもらうトビイロシワアリ |
|
|
|
| ●虫こぶをつくる |
| アブラムシの中には寄主植物に虫こぶをつくるものがいます。虫こぶをつくる虫はハエなどいくつかいますが、アブラムシもそのひとつです。アブラムシが出すある種の物質によって、寄主の細胞が膨れてできます。虫こぶの中はかっこうの巣となっています。寄主植物のさまざまな部位にできます。サクラの葉のヘリ、エゴノキのシュート、ケヤキの葉の表面などに見られます。 |
 |
 |
 |
| ヌルデにできた虫こぶ(ヌルデミミフシ)(左)と虫こぶの形成者(ヌルデシロアブラムシ)(右) |
|
 |
 |
 |
| サクラにできる2種の虫こぶ:サクラハチジミフシ(形成者はサクラコブアブラムシ)(左)とサクラトサカフシ(右)(形成者はサクラフシアブラムシ) |
|
|
|