 �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� |
 |
���m�u�h�E�i�A���j
 |
| ����t����W���ꏊ�̈ړ�����r���̎Ζʈ�ʂɃm�u�h�E����R�̎���t���Ă��܂����B
|
 |
 |
| ����ȃm�u�h�E�̎��ƃm�u�h�E�~�^�}�o�G�ɂ�钎���� |
| (���јa�T) |
|
|
 |
�m�u�h�E������t���Ă��܂��ˁB���̒��ɂ́A����������̂悤�Ɍ����܂����������ɓ��荞��Ŕ�債�����̂�����܂��B�ӂ�ӂ킵�đ傫���_�炩�����͖{���̎��ł͂Ȃ��āA�����Ă݂�ƒ��ɏ����ȗc���������Ă��܂��B����͒����Ԗ��͒������ƌ����܂��B�����͖̂{���̎��ŁA���ɃE������Ɠ����j�Ƃ���������ɕ�܂ꂽ�����킪�����Ă��܂��B
���̒����Ԃ̓m�u�h�E�~�^�}�o�G�ɂ���č���Ă��܂��B12���ɂ͒����Ԃ��ڂ�����������Ă���搶�̍u�K�����̂Ő���Q�����Ă��������B(����) |
|
 |
|
 |
|
|
���G�m�R���O�T���i�A���j
 |
| ���X�^�[�g�n�_�̍L��ɁA�u�L����炵�v���Q�����Ă��܂����B�悭����Ƃ������̎�ނ�����Ƃ����̂ł����c |
 |
| (�傫�ȕ���w����)����A���h�ł���ˁB����́A�F��������������Ȃ��݂̗L��L����炵�ł��B�L����炵�̓G�m�R���O�T�̒��Ԃ̂��Ƃł����A�G�m�R���O�T�Ƃ����Ă��F�X����܂��B6��������o�Ă�����̂͂قƂ�ǂ��G�m�R���O�T�ŁA�䂪�����Ɨ����Ă��܂��B�x���Ȃ��ďn���A���傤�Ǎ����䂪���ꉺ�����Ă���̂��A�A�L�m�G�m�R���O�T�ł��B |
 |
 |
| �G�m�R���O�T��������鑺�c�搶 |
|
|
 |
�ŋ߁A�s�X�n�ɂ��̎����ł��G�m�R���O�T���ڗ����܂��B�G�m�R���O�T�̓A���J�����̓y����D�ނ̂ŁA�s�X�n�̃R���N���[�g�⑤�a�̂Ƃ���ɐ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�����10�`20�N�O�ɂ͂Ȃ��������ƂȂ̂ŁA��x�O���ɏo���G�m�R���O�T���o�߂�ŋA���Ă������̂ł͂Ȃ����Ƃ��l�����Ă��܂��B
���������͂��낢�날��܂����A�t�ɖт�����̂��G�m�R���O�T�A�Ȃ��̂��A�L�m�G�m�R���O�T�ł��B |
 |
�܂��A��̗� (����)���g�傷��ƁA
���G�m�R���O�T��䚂����ɏ��Ԃ̌삦�����S��������Ă���B
���A�L�m�G�m�R���O�T��䚂������珬�Ԃ̌삦�������������Ă���B
���L���G�m�R���O�T��䚂������珬�Ԃ̌삦�����قƂ�Ǐo�Ă���B
�Ƃ������_�ŋ�ʂ��ł��܂��B���̑��ɃR�c�u�L���G�m�R���A�A���Ƃ̎G��Ǝv����I�I�G�m�R���Ƃ����̂�����܂��B(���c) |
|
 |
|
|
 |
|
  �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� |
|
���Ζʗт̉��]�i�A���j
  |
 |
| �Ζʗт��ώ@���� |
|
 |
���������̎Ζʗт�����͍̂�����3��ڂł����A���ꂼ��̗̈Ⴂ��������܂����B
5���̎��́A���t���͉��A��Ύ��͔Z���ŐF�̍����傫�������ł��B
6���ɂȂ�ƁA���t������Ύ������Z���Ȃ��Ă��܂�Ⴂ������܂���ł����B
������9���A���t���̗t�����݂͂��߂Ă���A�N�Y���L�тĖ̏���Ă��܂��B
�߂�������ƁA�O��ώ@�����K�}�̑������͕̂䂪����͂��߂Ă��܂��B�����̂̐l�͊��c�ɂ��܂����B(���c) |
|
 |
|
�����Y�i����搶�j
 |
| �����̎����A���������烂�Y�̍������������܂��B
|
 |
���ꂩ�牽�����ŕ�������Ǝv���܂����A���̎������Y�͓d����̏��ō��������܂��B���Y�̐e��3�����ɐB�����āA�q��Ă��I���Ǝ����̂Ȃ����o�č����Ɉړ���2��ڂ̔ɐB�����܂��B
�M���ނ͕��ʎq�����꒣����o�܂����A���Y�͐e���o�Ďq�������̂܂c�莩�����������܂��B�e�͍����ł�2��ڂ̎q��Ă��I���ƁA�H�ɂ܂��q�������̂��鏊�ɖ߂��Ă��āA�Y���������N���܂ꂽ�q�����W�����꒣�葈�������܂��B
|
 |
�͂��߂͐����킩��A����Ɏ���g�ݍ����̌����������s���A�n��ɗ����邱�Ƃ�����A��̂Ђ�ɍڂ��Ă�����Ă��邱�Ƃ�����܂��B�꒣��������R�͉a�̊m�ۂ̂��߂ŁA���̓꒣����ʼna��T���A�����Ƃ��납���э~��ăg�J�Q��o�b�^��߂܂��܂��B
���Ɏg���G�l���M�[�͓����Ȃ̂ŁA�Ȃ�ׂ��傫�Ȋl�����˂炢�S���ɋ߂���ɒv�������������A�̂Ƃ��ȂǂɎh���܂��B������u�͂�ɂ��v�ł��ˁB
�t�̋����s���͗Y�����E�̊�̍������i�ߊ���j�����Ɍ��݂Ɍ����A���̎��ɐF�X�Ȓ��̖��������Ď��̋C�������܂��B�����̃��p�[�g���[�������������ɂ��Ă�悤�ł��B���G�O��̒��̐������Ƃ��ɂ̓��Y�̉\��������̂Œ��ӂ��K�v�ł��ˁB(����)
|
 |
 |
| ��������}�����q�K���o�i�ƁA���Y�̐��������铂��搶 |
|
|
|
 |
|
�����}�g�V���A�Q�i��ؐ搶�j
 |
| ����1��̊ώ@��œo�ꂵ�����}�g�V���A�Q���A�����ꏊ�Ŋώ@����܂����B�������A�t�Ƃ͏����悤�����قȂ�悤�ł��B |
 |
 |
| ���}�g�V���A�Q�Y�����t�^ |
|
 |
 |
| ���}�g�V���A�Q�Y�����Č^ |
|
|
 |
���̎Ζʂł̓��}�g�V���A�Q�������������܂��B�������A�t�Ɍ���ꂽ���̂Ƃ͑̐F���قȂ��Ă��܂��B���}�g�V���A�Q�͉ĂɎ��̐��オ�H������̂ł����A�t�͍̌̂��F�����Ă���̂ɑ��A�Ĉȍ~�̌̂̓x�b�R�E�F�����Ă��܂��B������40�N�O�܂ł́u�x�b�R�E�V���A�Q�v�Ƃ����ʂ̎�ނ̃V���A�Q���V���ƍl�����Ă��܂������A���̌㌤�����i�݁A������̕ʂ̌^�ł���Ƃ������Ƃ��������܂����B
���̃x�b�R�E�^(�Č^)�̌̂́A�W�������܂荂���Ȃ��ꏊ�i���쌧�ł͂��悻1000m�ȉ��j�ł����ώ@����Ă��܂���B�܂�A��n�ł͔N2���ł���̂ɑ��A�W���̍����i1000�`1500m�j�n��ł͏t�^�݂̂̔N1���ł���ƍl�����܂��B(�e�{) |
|
 |
|
���J�Â̋x�k�n�i�A���j
  |
 |
| �J�i���O���̗Y�ԂƂ� |
|
 |
�J�i���O���̉Ԃ��炢�Ă��܂��B�J�i���O���͎��Y�ي��ł��B�G��Ɣ��������o�܂����ˁB����͉ԕ��ŁA���̎����ڗ��̂͗Y�Ԃł��B�J�i���O���͕��}�ԂŁA���̉ԕ��������̌��ɂȂ�l�����܂��B
�J�i���O���ɂ͐L�т�����Ƌt�����̂Ƃ��������Ă��܂��B����ő��̐A���̏�ɔ����オ�葼�̐A�����Ă��܂��܂��B
�I�I�u�^�N�T�����������Ă��܂��B�x�k�c�̊J���n�ɂ͂܂��ŏ��Ƀu�^�N�T�����荞�݁A���̂��ƂɁA�I�I�u�^�N�T�A�Z�C�^�J�A���_�`�\�E�A�N�Y�Ȃǂ����荞�݂܂��B���̍��A�u�^�N�T�͂��܂茩���Ȃ��Ȃ�܂����ˁB(���c) |
 |
|
 �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� |
|
���W�����E�O���Ƌ���O���i��Ԑ搶�j
 |
| ���������f����悤�ɑ傫�ȃN���̑��������Ă��܂��B��������グ�Ȃ���A��Ԑ搶�̉���ł��B |
 |
 |
3��̃N�����Z�ޑ�
�E�[�̓_���V���J�l�C�\�E���E�O�� |
|
 |
�����ɑ傫�ȃN�����Ԃ��Ă��܂��ˁB���̃N���́c�����A�W�����E�O���ł��B�ł��A�ʂ����Ă݂Ȃ���ɂ͂���ȊO�̃N���������Ă��܂����H
���͂��̖Ԃɂ�4�̑傫���̈Ⴄ�N�������܂��B��ԑ傫���̂̓W�����E�O���̎��̈����̂ł��B�����Ă��̉��ɂ��钆���炢�̃N�����A�W�����E�O���̗Y�̐��̂ł��B��ʂɖԂ�N���́A���̂ɂȂ�ƖԂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�W�����E�O���́A���̖Ԃɋ��ĉa�̂����ڂ��������Ă��܂��B�����E������Đ��̂ɂȂ�Ƃ����`�����X�ŁA�Y���߂Â���ڂ��܂��B
�Y�̋߂��ɂ��鏬�����N���̓A�V�i�K�O���̗c�̂ŁA�W�����E�O���̖Ԃ𗘗p���Ď����̖Ԃ��Ă��܂��B����ɁA�����Ə����Ȑm�O�̂悤�ȃN�������܂��B����̓V���J�l�C�\�E���E�O���ŁA���ĖԂɂ������������ȉa�𓐂�Ő������Ă��܂��B�W�����E�O���̖Ԃ͖Ԃ̖ڂ��ׂ����̂ŁA���̂悤�ɑ����̏����ȃN������������Ă��܂��B(�e�{)
|
|
|
 |
|
���}�e�o�V�C�i�A���j
 |
���ɑ傫�ȃh���O�������������Ă��܂��ˁB
������5�A6���̂���}�e�o�V�C�̉Ԃ��炢�Ă��܂����B���̉��ɏ������������Ă��܂����B���ꂪ�����ɂ����ς������Ă��܂��B�}�e�o�V�C��2�N�Ŏ����n�����Ƃ�������܂��B |
 |
 |
6���̃}�e�o�V�C
�Y�ԂƎ��ԁA�����ɑO�N�̉ʎ� |
|
 |
 |
9���̃}�e�o�V�C
�O�N�̉ʎ����n���Ă��Ă��� |
|
|
 |
| �}�e�o�V�C�͐�t���ɑ����ł����A�t�������̂ʼn������L�тȂ��Ȃ��č����Ă��܂��B��t���ł́A�}�e�o�V�C�̎}���C�ɑ}���ĊC�ۂ̎��t����Ђтɂ��Ă����̂ł��̖������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B(���c) |
|
 |
|
���g�b�N���o�`�̑��i�c���搶�j
 |
| ���R���N���[�g�ō��ꂽ��̓y��ɁA�D�łł����c�q�̂悤�Ȃ��̂�����t�����Ă��܂��B����͎��̓n�`�̑����Ƃ����܂��B |
 |
|
|
 |
����̓g�b�N���o�`�̒��Ԃ̃X�Y�o�`�Ƃ����n�`�̑��ł��B�����̂��тꂪ��̂悤�ɖc��Ă���̂ł��̂悤�ɌĂ�Ă��܂��B�g�b�N����̑������n�`�̒��ł͓��{�ő�̎�ŁA�����̃g�b�N����̕�������ׂĂ��������A�Ō�ɂ͑S�̂�D�ŕ����ĉB���Ă��܂��܂��B���̑���1��������������܂���̂ŁA���܂肢���ꏊ�ł͂Ȃ������̂ł��傤�B |
|
 |
| �����̌�A�@�ʂɐ������͑��̏�ɁA�ʂ̃g�b�N���o�`�̑���������܂����B |
 |
 |
| �L�A�V�g�b�N���o�`�̑� |
|
 |
| ������̓L�A�V�g�b�N���o�`�̑��ł��B�X�Y�o�`�̂��̂Ɣ�ׂ�Ƃ͂�����Ƃ����g�b�N��������Ă��܂��B���̂悤�ɐA���̌s�ɑ�����邱�Ƃ������A���ꂼ�ꗣ�ꂽ�Ƃ���ɍ�邽�߁A��x�ɂ�������̑����ώ@����͓̂���ł��B����́A�Z�C�{�E�Ȃǂ̊I�ɑS�ł������邱�Ƃ������悤�ɂ��Ă���̂��ƍl�����܂��B |
 |
| �悭�u�n�`�̊ώ@�����Ă��Ďh���ꂽ�肵�܂��H�v�Ƃ������������܂����A��I�̓ł͐ߑ������ɂ̂��ʂ�������̂Ȃ̂ŁA���Ɏh���ꂽ�Ƃ��Ă����邱�Ƃ͂���܂���B�X�Y���o�`��A�V�i�K�o�`�Ƃ������Љ�̃n�`�́A�W�c�Ő��������ŃN�}�Ȃǂ̑����P���M���ށA���ނɑR���邽�߂̓ł����悤�ɂȂ����̂ŁA��X�q�g�ɂ����ʂ�����̂ł��B(�e�{) |
|
|
| �i���c�j |
|
  �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� |
|
���J�j�N�T�i�A���j
 |
�V�_�A���̒n�㕔���͂قƂ�ǂ��t���ςł��B���̃J�j�N�T���`�͕ς���Ă��܂����A�V�_�A���ł��B�ʏ�̗t�͂����ɗt��������A�����1���̗t���ƕ�����܂����A���̃J�j�N�T�ł͂ǂ��ł��傤���H
���́A���̂�S�̂�1���̗t�ł��B�J�j�N�T�͗t�̐�[���������ĐL�тĂ����܂��B
�J�j�N�T�ɂ͉h�{����邾���̉H�ЂƖE�q�X��t����H�Ђ�����܂��B�E�q�X��t����H�Ђ͗t�̐�̕��ɕt���܂��B
�J�j�N�T�̐�̕��������̋�Ō͂�Ă��܂��ƁA���̎�O�̒Z���H���̐�̏��H�Ђ̊Ԃɂ���肩��t���L�тĂ����܂��B(���c)
|
 |
 |
�h�{���Ƃ�H�Ёi���j��
�E�q�X��t�����H�Ёi�E�j |
|
 |
 |
| �J�j�N�T�̖E�q�t�̗��� |
|
|
|
|
 |
|
���c���N�T�i�����搶�j
 |
 |
| �Q������c���N�T |
|
 |
 |
| �c���N�T�̉� |
|
|
 |
�c���N�T�̉Ԃ��悭���Ă��������B
���F���ނ��ڗ���3�{�̒Z���Y���ׂɂ͖����̂���ԕ����ł��Ȃ����߁A���Y���ׂƌ����܂��B�����͒����ĂԂ��߂̂��̂ł��B
���̑O�ɂ���1�{�ƈ�ԑO�ɂ���Q�{�̗Y���ׂɂ͖����̂���ԕ����ł��܂��B�����ׂ͒���2�{�̗Y���ׂ̊Ԃ�1�{����܂��B
�c���N�T�̎̎d����2 �ʂ肠��܂��B��ڂ͏����ȃq���^�A�u��n�i�o�`�Ȃǂɂ��ŁA��ɌߑO���ɍs���܂��B��ڂ͓����Ԃ̒��ŋN���铯�ԎŁA�������A�����ׂƗY���ׂ��ۂ܂��Ă��āA���̎��ɋN����܂��B�Ԃ��J���Ƃ������Ԏ����܂��B(���c)
|
 |
| ���R�ώ@��w�u���O(��)�ɂ��ڍׂȐ���������܂��̂ŁA���킹�Ă������������B |
|
  |
|
���N���̎��i�A���j
  |
 |
| �N���̎��̂������������␣�搶 |
|
 |
�����ɏH�̖��o�̃N��������܂��B�N���̖Ɏ����ɃN�k�M������܂��B���̌`�ŊȒP�ɋ�ʂł��܂����A�����Ȃ����͗t�Ō������܂��B�t�̉��̋����̐�܂ŗt�Αf�������ėΐF�Ȃ̂��N���ł��B�t���}�����ɗ����Ă���悤�Ɍ�����̂��N�k�M�A����Ɍ�����̂��N���ł��B
��q�A���ł͎�q�͎��Ƃ�����ɕ�܂�A���̒����͂����Ă��܂��B��q�͎q�[���ς�����ʎ��ɕ�܂�܂��B�N���̉ʎ��͌����ʔ�ɕ�܂ꒆ�ɂP�̎�q������܂��B
��q�̒��͗{����~�����q�t�Ŗ�������A�����H�ׂĂ��܂��B(���c) |
 |
|
 �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� |
|
| ���J���l�Y�~�̑��i��Ԑ搶�j |
| �����n�т̃J�����\�t�g�{�[����Ɋۂ߂��Ă��܂����B��Ԑ搶�̉���ł��B
|
 |
 |
| �J���l�Y�~�̑�
|
|
 |
�C�l�Ȃ̑傫�ȐA���̂ŃJ���ƌĂт܂����A�������̃J�����ۂ܂��Ă���̂������܂����H�@����̓J���l�Y�~�̑��ł��B�J���l�Y�~�͓��{�ōł������ȃl�Y�~�ŁA�d����7g�A500�~��1������������܂���B�S�̂̓I�����W�F�ŕ����̖т͔����A�����K���������ł��B�J���l�Y�~�̑��͒��̑��ƈႢ�A�o�������������Ȃ��悤�ɍ���Ă���̂Ŏ��ʂ͊ȒP�ł��B�܂����ނ��^��ł��钹�ƈႢ�A�߂��̃J���𗘗p���đ�������܂��B���ɗΐF�̗t���������Ă��邩�ǂ����ŁA���g���Ă��鑃�������łȂ�����������܂��B�s�����a��10m�قǂ����Ȃ��̂ŁA���̒��ɐ������Ă������߂ɕK�v�Ȃ��ׂĂ�������Ă���K�v������܂��B���̂��߁A���w�W�����Ƃ��Ă��d�v�ł��B(�e�{) |
|
|
 |
|
�������i��������j
 |
| ������̊ώ@��̎Q���҂ŁA�J�Î�l�ł����鍡������ɁA���n�����}�������Ăɂ��ĉ�����Ă��������܂����B |
 |
���ẮA�̂̒����̍c�邵���H�ׂ��Ȃ������Ăł��B�F�f�������A���̐F�f�̒��ɉh�{������܂��B��������͎��R��1��1�������Ă����܂��B
6���Ɏ���܂��A10���Ɋ�����܂��B��v�ň�Ă₷���A���邿�Ă�����Ăƍ�Ǝ���������Ă���̂ŏ������Ă��܂����A1�����������̂Ŏ��n�ʂ����Ȃ��ł��B�H�ו��́A���邿��1���ɍ��Ă���1��2�t����Đ������Ƃ������ł��B
���n�������݂�����Ă����Ď��̔N�ɂ܂��Ă�����A����ɔw�䂪�Ⴍ�Ȃ��Ă��Ă��܂��܂����B���̏ꏊ�̍��Ăƌ�z�����Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ����ȂƎv���Ă��܂��B
�����˂ł́A���āA�ԕāA�ΕĂ������Ă��܂��B���Ă͍��̐F�f�A�ԕĂ͐Ԃ̐F�f�A�ΕĂ͗̐F�f�������Ă��܂��B(���c)
|
 |
 |
| ���Ă̕� |
|
|
|
 |
|
���c�`�C�i�S�ƃ}���n���~���E�i�R��搶�j
 |
| ���J�Ò��Ő������̃o�b�^�ނ��ώ@���邱�Ƃ��ł��܂������A���̒��ł��悭�ڗ������c�`�C�i�S�ƁA�o�b�^�ނ̓V�G�̃}���n���~���E�ɂ��āA�R��搶�̉���ł��B |
 |
|
|
| �c�`�C�i�S�̗c���i���j�Ɛ����i�E�j |
|
 |
| ���̃c�`�C�i�S�́A�c���̂Ƃ��͗ł����A�����͒��F�ł��B�c���̎��������Z���̂ŁA������1�ߖڂɂ���ۖ����ώ@���邱�Ƃ��ł��܂��B�o�b�^�̒��Ԃ͂��ׂĂ�����܂炸�ɕ���̂ŁA���Ă͒����ڂƌĂ�Ă��܂����B |
 |
 |
| �}���n���~���E |
|
 |
���āA���̃c�`�C�i�S�͗���n���ɎY�ނ̂ł����A���̗����H�ׂ鍩�������܂��B���ꂪ���̃}���n���~���E�ł��B�����ɂȂ�ƐA���H�Ń}���ނ̗t��H�ׂ�̂ł����A�c���̎��͓����H�Œn���̗����H�ׂ܂��B�̉t�ɂ̓J���^���W���Ƃ����������܂܂�Ă���A�畆�ɂ��Ɛ��Ԃ�����N�����łƂ��Ēm���Ă��܂����A���Ă͖ѐ�����Ƃ��ė��p���ꂽ���Ƃ�����Ƃ����܂��B�n���~���E�Ƃ������O�ł����A�ʏ�̃n���~���E�̓S�~���V�ɋ߂���ł���̂ɑ��A���̃}���n���~���E���܂ރc�`�n���~���E�Ȃ̓J�}�L�����h�L��A�����h�L�ɋ߂���ł��B(�e�{)
|
|
 |
|
���ʎ����z���J�����V�i����搶�j
 |
���c�e�̔r���H�ɖ��Ă����A�A�J���K�V���ɂ́A�Ԋ��F�ŁA���ۂ��ڗ��I�I�z�V�J�����V���Q�����Ă��܂����B�悭����ƁA���������̗t�̗�����7�`8�C�A�t�e�ɉB�ꂽ�ʎ��ɐ��C�A��2?�̑傫���̐��������܂����B�߂��ɂ͂�⏬�Ԃ�̃q���z�V�J�����V�����܂����B
����搶�̐����ɂ��ƁA�z�V�J�����V�ނ̓~�J������̉ʎ����z�`���邱�ƂŒm���Ă���Q���ł��B�����̃z�V�J�����V�͖{�B�ȓ�ɐ������A�����͉z�~�ɓ���O�ɁA�{���������킦��Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɃN�Y�ɂ���}���J�����V�͌s�t��䰂���A�O��̔_��Ŋώ@�����A�N���w���J�����V�̓C�l�䂩��A�z�~���̗{�����m�ۂ��Ă���Ƃ̂��Ƃł��B
|
 |
 |
| �I�I�z�V�J�����V |
| (�����j) |
|
|
|
|
 |
|
|
  �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� �y�[�W�g�b�v�ɖ߂���
|
|
���N�̉����ˁE�s���J�Âł̊ώ@��͍���ŏI���ł��B1�N�Ԃɂ킽�育�x�������������䑷�q�s�E���̕��X�ƒJ�Î�l�̊F�l�A�u�t�̐搶���A�����ĎQ���҂̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂����B
��O�ώ@��̊F�Ώ܂̂��邵�ł�����C���ł����A���N��30���ȏ�̕��ɂ��n�����邱�Ƃ��ł��܂����B
|

|
 |
| �ώ@��C����A�V�w���̓���搶���C�������^����܂��� |
|
 |
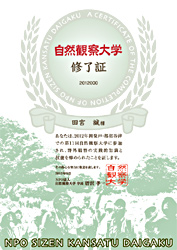 |
| 2012�N�x
�C���� |
|
|