 |
| �@1�����o���ĥ��
�����˂̂��̌� |
�O��A5���Ɋώ@�����A���́A���̌�ǂ��Ȃ����ł��傤���B
�������̃A�J�}�c�́A�O��͗Y�ԁA���Ԃ������܂������A����A�Y�Ԃ͂��ׂė����A���ԁi�ԕ�j�����傫���Ȃ��Ă��܂����B�V�}�̊�ɗΐF�̋��ʂ����Ă��܂������A����͍�N�̎��ԂŁA���N�̏H�Ƀ}�c�{�b�N���ɂȂ邻���ł��B
���Ă̐A������������ώ@�ł��܂����B�O��Ԑ��肾�����n���W�I���͖ڗ����Ȃ��Ȃ�A����̓q���W���I���̉Ԃ���ʂɍ炢�Ă����ق��A�I�J�g���m�I�A�^�J�g�E�_�C�A�A�L�J���}�c�A�N�T�t�W�A���u�W���~�Ȃǂ������܂����B�O�����I���u�W���~�͉Ԃ̎������I����āA���������n�߂Ă��܂����B���͐������������A�����M�A�Z�C�^�J�A���_�`�\�E�A�X�X�L�Ȃǂ������L�тĂ��܂����B
�ѓ��̓��ł́A�V���J�V�̎}����t�̐V����ւ������܂����B��[�ɂ��̏t�L�т��V�����}�A���̊��H��ƑO�N�L�т��}�A����Ɋ�ɂ͂����ƑO�̎}������A3�N4�N�o�����Â��t�����Ă��܂��B�V���J�V�͏�Ύ��ł����A��Ύ��͗t���܂����������Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�Â��t�������鎞���ɐV�����t���o�邽�߁A��ɂǂ�������ɗt�������ԂȂ̂��Ƃ������Ƃ͂����m�̒ʂ�ł��B��Ύ��̗t�́A�����������ď�v�ł��B
����A�V���J�V�ׂ̗�ɂ́A���t���̃��N�m�L�������Ă��܂����B���t���͂��̎����A�S�̂��V�����t�ɐ����ς���Ă��܂��B�t�̎����͒Z���A4�`10�����ɂ����t���Ȃ����Ƃ���ėΎ��Ƃ������܂��B�t�͈�ʂɔ����̂ŁA��ŐG���Ĕ�ׂĂ݂�ƁA��Ύ��Ƃ̈Ⴂ���悭������Ǝv���܂��B |
|
|
| �Ζʗт߂Ă݂�ƁA5���̊ώ@��̎������Z���Ȃ�A�O�ςł͏�Ύ��A���t���̋�ʂ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�H�ɂ́A�܂��ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤����� |
|
|
|
�A�J�}�c�̐V�}�ɍ��N�������ԕ�B���H�}�c�{�b�N���ɂȂ�܂��B���H�}�c�{�b�N���ɂȂ鋅�ʂ́A������������Ƒ傫���A�}�̊�ɂ��Ă��܂��B |
|
|
|
| ���ẲԁX���炢�Ă��܂����B |
|
|
 |
|
|
�I�J�g���m�I
���̖��̒ʂ�A�Ղ̂����ۂ̂悤�ɉԂ��[��ɂ��܂��B |
|
|
|
|
|
 �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� |
| �@�����̃��V���W�܂�N���̉� |
�N���̉Ԃ͏I���ɋ߂��A�x�炫�̗Y�Ԃ��炫�A���̓Ɠ��̓����ɗU���Ē��������W�܂��Ă��܂����B�Ԃ̖���ԕ������߂ďW�܂鍩��������A�����_���N�������܂��B
�N���̉ԏ��͂قƂ�ǂ��Y�ԂŁA���Ԃ͊�̕����ɂ��Ă��܂��B
�Ƃ���ŁA�C�K�̒��ɓ����Ă�����̐��́A�ԏ��ɂ����Ԃ̐��Ɠ��������āA�m���Ă܂������H
���Ԃ�3�`4�Ȃ�A���̐���3�`4�Ȃ̂������ł��B�H�ɂȂ��ăC�K�O���������Ă�����A���g�𐔂��Ă݂܂��傤�B |
| �Q�l�F�w�Z��̎��x |
|
|
|
�N���̖ɏW�܂钎���ώ@���Ă��܂��B
�N���̉Ԃɂ��܂��Ă��������F�Z�}�_���R�K�l�A�q���^�n�i���O���A�V���e���n�i���O���A�A�I�J�~�L�����h�L�A�J�g�E�J�~�L�����h�L�A�L�^�e�n�A�q�J�Q�`���E�A�L�}�_���Z�Z���Ȃ� |
|
|
|
|
| �E�炵������̃L�A�Q�n�����ނ�̗t���ςɎ~�܂��Ă��܂����B�E�璼��͒�R�͂��\���ɂ��Ă��Ȃ����߁A���������ĕ߂܂����肹���A�����ƌ�����Ă����邱�Ƃ��厖�ł��B |
|
 |
|
|
�щ��̑����ɂāB���ẮA���������ɂƂ��ė��̋G�߁B
���ʐ^����Ă����������Q���҂̍╔�d�h����H���A�u��t�𑁂��ς܂����̂ŁA��ɃX�^�[�g�n�_�֏o�����A����ƂȂ��߂�������Ă݂܂����B����ƁA�N�T�t�W�₻��ɋz������N�}�o�`�A�J�����V�A�L�U�n�V�I�j�O���ȂǁA�n�܂�܂ł̂킸���Ȏ��ԂɊ���̐������ɏo����Ƃ��ł��܂����B���s���͎O���̓��H
�����������ŁA�J�m�R�K�i�L�n�_�J�m�R�j�̐F�N�₩�ȉ��F���ڂɗ��܂�A���y���݂̂Ƃ��뎸�炵�āA�p�`���ƂP���B�点�Ă��炢�܂����B�v |
|
|
|
|
 |
| �@�����˂̖L���Ȏ��R���ے����鐶�������� |
�т̒��ɁA���j�[�N�Ȍ���s�����Ƃ�V���A�Q���V�̒��ԁA�K�K���{���h�L�����܂����B�����̍ہA�Y���a���g���Ď���U�����Ƃ��m���Ă��܂��B
�a��߂܂����Y�́A�a��������܂ܑ���}�ȂǂɂԂ牺����A�t�F���������o���Ď���҂��܂��i���ׂĂ̎�ł͂���܂��j�B���͉a�ɂ��Ă���ė��܂��B�����a��H�n�߂�ƁA���̊ԂɌ�������Ă��܂��Ƃ����킯�ł��B
�����͉a���������Y�ɏo����Ƃ͂ł��܂���ł������A�ʂ̓��ɍu�t�̗�ؐ搶�ɂ��A�m���ɉa�������Ă���Y�̎p���m�F����Ă��܂��i�c�O�Ȃ��玓�͂���ė��܂���ł������j�B |
|
|
| �a�������o���i�H�j�K�K���{���h�L�Y�B����҂������B |
|
�� |
|
|
| �ł��A�҂������т�ĥ�����
��������������B���������̎��ւ̃v���[���g��H�ׂ��Ⴂ�܂����B |
|
|
| ���a40�N��܂ł́A�֓��n���ł����n�тɕ��ʂɐ������Ă����ł��낤�K�K���{���h�L�́A��n���̐i�s�ƕ��n�т̏����ƂƂ��ɁA�������炵�Ă����Ă��܂��B���Ȃ̃��b�h�f�[�^�u�b�N�ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ����̂́A��t���A��ʌ��Ȃǂ̃��b�h�f�[�^�u�b�N�ł́A���}�g�V���A�Q�ƂƂ��ɁA���ی쐶���Ɏw�肳��Ă��܂��B�����ꏊ������A�p���������Ȃ��Ȃ������A�����˂̎��R���̖L�����Ɋ��Q�����ɂ͂����܂���B |
|
3�ӏ��ŁA�z�I�W���̗Y�̂������肪�������܂����B�d����S���t��̃t�F���X�̏�A���̒��ȂǂɎ~�܂�A�����Ă��������Ă��܂��B
�s�S��s�s�����ꂽ�n�悩��͂�������p�������Ă��܂��܂������A���������˂ł͍��ł��������ʂɌ����钹�ł��B�������A����Ŏ��ӕ��̑�n���A�����ŕ����������c�Ȃǂ̑J�ڂ��i�ނ��Ƃɂ���đ����k�n�^�̊��������Ă��܂��A�₪�Ă͎p�������Ă��܂��\�����Ȃ��Ƃ͂����܂���B���ɂ́A�����������_����A��t�����u�z�I�W���v���������Ă݂܂��傤�B |
| �Q�l�F�w�쒹���m����x |
|
|
|
| �z�I�W���i�o�T�F�w�쒹���m����x�j |
|
|
|
|
 �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� |
| �@�N�������̂��낢��Ȑ��� |
�O��ꂽ�W�����E�O���̂܂ǂ��i���̂�����o�Ă����q�O�����A���炭���ӂŌł܂��ĉ߂������Ɓj���������āA���������ɏ����ȖԂ��ł��Ă��܂����B�����Ȃ����́A�p����͑��̃N���ƌ����������ɂ����̂ł����A�Ԃ�����A�ڂׂ̍�����A�O��ɒ���ꂽ�s�K���Ȏ�����A��ʂł���Ƃ̂��ƁB�Ă̏I���ɂ́A�N���������Ɛ������A�傫�ȖԂ��ڗ��悤�ɂȂ�܂��B
�j�K�L�̗t���ςɂ��傱��Ə���Ă����̂́A�T�c�}�m�~�_�}�V�B�[���`��ɂ����đf�����Ԃ�̂ŁA�ώ@����̂ɂ����Ă����ł��B���Ȃ̎��R�����ɂ������ł��傤���B
�X�X�L��V�̗t��܂肽���̂́A��̒N�̎d�Ƃł��傤�H ���ɂ���̂́A���}�g�R�}�`�O���������ł��B�����t�N���O���ނ́A�A���Ȃǂ̓V�G�ɐH�ׂ��Ȃ��悤�A�t���ς�܂�Ȃ��č�����Y���̒��ŎY�����܂��B�ǂ�Ȃɒ��g���C�ɂȂ��Ă��A�����ƌ����܂��傤�B
�S���̂����I�݂ȖԂőO��b��ɏ�����A�I�I�q���O�������܂����B�ׂ����̉��̕��������[�y�ł悭���Ă݂�ƁA�m���ɗ���Ɍ���S���������܂����B�_���S���V�Ȃǂ��������Ɠ����Ɏ�����āA�݂�グ����Ƃ����d�|���ł��B
�����L�т�����אڂ����S���t��̃t�F���X�ɂ́A�傫�ȉ~�Ԃ����R�K�l�O�����ڗ����܂����B�Ԃ̒����ɂ�X����̉B��т�����A�̂������ۂ�Ǝ��܂�܂��B�a���L�x�ȑ������D�ރR�K�l�O���́A�ߔN�A���̐������炵�Ă���Ƃ����܂��B8�ӏ��Ŋώ@���邱�Ƃ��ł������Ƃ́A���̉����˂��A�a�̖L�x�Ȋ��ł��邱�Ƃ���Ă��܂��B
�W���ꏊ�ł́A�M�U�M�U�̉B��т������i�K�R�K�l�O���������܂����B�ԂɎ��G��Ă݂�ƁA����ɖԂ�h���Ԃ��Ă��܂��B��������ƉB��т͏c�̈�{�ɂȂ邻���ł��B |
| �Q�l�F�w����
�Z��̃N���E�_�j�E�A�u�����V�x |
|
|
|
�R�K�l�O���Ƃ��̖�
�B��тƑ̌^���҂�����B |
|
 |
|
|
| �t�N���O���ނ̗��̂��������Ă���悤�ł����A�����ĊJ���Ă͂Ȃ�܂���B |
|
|
|
|
|
 |
| �@�G�m�L�̊��Ō����A���ƃA�u�����V�̊W |
�щ��̓��A�ɐ����Ă����G�m�L�̊��ɁA����獕���e�������܂��B���̐��̂́A�N���N�T�A���B
�����āA�A�����W�܂��Ă��镔�������[�y�ł悭���Ă݂�ƁA�A�u�����V�����܂����B
�N���N�T�A���Ɉ͂܂�Ă����̂́A���m�N�`�i�K�I�I�A�u�����V�ŁA���O�̒ʂ���������A�̒�5mm�قǂ̑傫�ȃA�u�����V�ł��B�A���ɐG���āA�A�u�����V�����K����ØI�̗����o���Ă���̂������܂����B
���m�N�`�i�K�I�I�A�u�����V�́A�G�m�L�̔���i�Ђ����j�ɍ��������j�ŁA�t�ǂ���`���z���܂����A���̌��j�͔��ɒ������߁A�����ɂ͈����������Ƃ��ł��܂���B�܂�A�V�G�ɏP����\���������̂ł��B���̂��߁A�ØI��^�������Ɏ���Ă��炤�A���Ƃ̋����W�́A���̏ꍇ�A�ǂ�ȃA�u�����V�������ł��Ƃ����܂��B
��ʓI�ɗ��҂́A�a���i���ǂ��j�Ƃ����y��h�肱�߂��g���l���̒��ɂ���̂ł����A�����ł͉��炩�̗��R�ŋa�������Ă������߁A���̗l�q���ώ@���邱�Ƃ��ł����̂ł����B |
| �Q�l�F�w����
�Z��̃N���E�_�j�E�A�u�����V�x |
|
|
|
|
|
�� |
|
|
���m�N�`�i�K�I�I�A�u�����V�ƃN���N�T�A�������܂����B
�A�����A�u�����V�ɌQ����A�ØI��������Ă��܂��B |
|
|
|
|
 �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� |
| �@���ʂɂ��A���̈Ⴂ�����Ă݂悤 |
���n�ɉԕ�������K�}�����������Ă��܂����B
�K�}�ɂ́A�K�}�E�q���K�}�E�R�K�}�̂R�킪����A����̗Y�ԕ��i�䂤�������j�Ɖ����̎��ԕ��i���������j���������Ă���ƃK�}���R�K�}�A�������Ă��Ȃ��ƃq���K�}�ł��B
�K�}�Ƃ����A�Î��L�́u�����̔��e�v�B�є�����ꂽ�ɂ݂��K�}�̕�Ȃɂ���܂��Ď��������e�̘b���L���ł����A���ۂɖ��������̂́A�����i�ق����E�ق����j�Ƃ����Ċ����ł��p�����Ă���K�}�̉ԕ��̕��Ȃ̂������ł��B���e�́A�{���́A��Ȃł͂Ȃ��ԕ��ɂ���܂����̂�������܂���B
�K�}�̖T�ɂ̓��V�ƃI�M�������Ă��܂����B�n�����ʂ������Ƃ��납��Ⴂ�Ƃ���ɂ����ăK�}�A���V�A�I�M�̏��ɕ��z���Ă��܂��B�����̐A�������邱�ƂŁA�y�n�̎�����m�邱�Ƃ��ł��܂��B
�A���́A���̕ω��Ǝ��Ԃ̌o�߂ɉ����Ĉڂ�ς��܂��B�x�k�c�₻�̎��ӂł́A�ŏ���1�N�����{�Q�����������̂��A�����o�ɂ�āA���N�����{�Q���A�ؖ{�Q���ւƑJ�ڂ��Ă����܂��B |
| �Q�l�F�w�ʐ^�Ō���A���p��x
|
|
|
|
 |
|
|
�Ζʗё��ɐ����Ă���I�M
�l��������ŃK�}�A���V�Ɛ��ݕ����Ă���B |
|
|
|
|
|
�c��ڂ̘e�̗p���H���A�S����m�̃A�I�_�C�V���E���j���ł��܂����B
���͂ǂ��ɂ���̂ł��傤���H |
|
|
|
 |
| �@�n���m�L�L�N�C���V����݂��Ζʗт̕����z�� |
�ѓ��Ō������ٗl�ȃA�J���K�V���B�͂ꂽ������A�Ƃ���Ă�̂悤�Ȃ��̂���������o�Ă��܂��B��̉��Ȃ̂ł��傤�B
����́A�����Ɩ̋����琬��t���X�ƌĂ����́B�͂�ɐ��������n���m�L�L�N�C���V���؎������@��i��ʼn����o�������̂ł��B
�����̑̒��͂킸��2�o�قǁB���́A���̒��ɑ������A�Y���̍ہA�w���ɒ������Ă���A���u���V�A�ۂƂ����ۂ̖E�q���܂��܂��B���ꂪ�B���ǂɔɐB�A�z�������c���́A���̋ۂ�H�ׂ�匂ɁB���̌�A�H�����������͌�����āA���͌͂����E�o�A�V���Ȍ͂�ւƈړ����A�Y���A�ɐB����Ƃ����T�C�N�����J��Ԃ��܂��B��������̑O�Ɏ�荞�ދۂ̖E�q�́A�Y���𑣂����ƂƂ��ɁA�V�������ōĂїc���̐H�ƂƂȂ�̂ł��B
�������āA�n���m�L�L�N�C���V�ƃA���u���V�A�ۂ͋��ɕ��z���g�傳���A�͎��������̉�́E�����𑣐i���Ă���̂ł��B�A�J���K�V�����͂��߁A�X�тɂ��������ł���z���́A���邢�������ł͑f�����������܂����A�Â��������ł͐����ł��܂���B���̂��߁A�X�т̑J�ڂɔ������̎��킪������ƁA�\���Ȍ��𗁂т��Ȃ��Ȃ�A�͎�����^���ɂ���܂��B�ꕔ�ł͊Q���Ƃ����L�N�C���V�ł����A�Ζʗтɂ�����J�ڂ╨���z�Ƃ����ϓ_���猩�Ă݂�ƁA�ނ�͐X�̌��S�ȃT�C�N�����ێ����邽�߂ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ������҂Ȃ̂ł��B
|
|
|
| �n���m�L�L�N�C���V�����݂��Ă���͎������A�J���K�V�� |
|
 |
 |
| �n���m�L�L�N�C���V�����i�B�e�F�~�J����j |
|
|
|
|
 �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� �y�[�W�g�b�v�ɖ߂��� |
| �@�����������̐����c�苣�� |
�O��̊ώ@��ł́A�g�E�L���E�q���n���~���E�̗c����ނ�u�n���~���E�ނ�v�V�т��b��ƂȂ�܂������A
���̗c�����A���Ă̂��̎����Ɋ��������}�����c���A���o�`�ɏP����Ƃ̘b����A�������Č���������̃Z�b�g�Ŋώ@���܂����B�����A�Z�b�g�̒��ł̐킢�͓r���Ŏ��Ԑ�ɏI����Ă��܂����̂ŁA����ǂ��Ă����炢���Ă����܂��傤�B
�c���A���o�`�̐j�ŁA�e�̉��ɖ������������ꂽ�g�E�L���E�q���n���~���E�B���X�ɓł����A���S�ɓ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�����ɓ��荞�c���A���o�`�́A���̉��̕�������ď_�炩�����܂��B�����āA�g�E�L���E�q���n���~���E�̕����̕\�ʂɗ����Y�݂��A�����ɍ������l�ߊW�����Ă��܂��܂��B�������āA�����́A�c���A���o�`�̎q�ǂ��̂��߂̗h�肩������ɂȂ��Ă��܂��Ƃ����킯�ł��B |
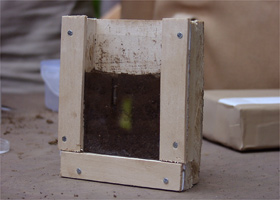 |
| ����ȑ��u�Ŋώ@���Ă݂܂����B |
|
 |
|
|
| �c���A���o�`���g�E�L���E�q���n���~���E�̗c���ɐj���h�����Ƃ��Ă��܂��B |
|
|
|
�R�[�X�I���_�̃��V�Q���ł��������Ă����̂́A�I�I���V�L���̗Y�ł��B
���̑���_���������܂��B�ώ@���1�T�ԑO�̉����̎��ɂ́A���V�Q����ՂޏZ��n�̓d����e���r�A���e�i�̏�ł��������Ă����̂ł����A�����͎p�������������������Ȃ������̂ŁA�u�t�̓���搶���������s���܂����B�J�b�R�E�ł��B
�J�b�R�E���A�I�I���V�L���ɑ��Ċ��ł���̂���ł��B���̑��ɗ����Y�݁A�h��ɗ������߂�������A�z�������̎q��Ă܂ł�点��Ƃ����K���ŁA�z�g�g�M�X�Ȃǂɂ������܂��B
�J�b�R�E�́A�I�I���V�L���̑�������̎���_���ė����Y�݂��A�����ɃI�I���V�L���̗���1���o���Ď̂ĂĂ��܂��܂��B�܂��A�z�������J�b�R�E�̐��́A�����̃I�I���V�L���̗����O�Ɏ̂āA�a��Ɛ肵�Ă��܂��܂��B����A�h��̃I�I���V�L���̑����A�J�b�R�E�̗����������Ď̂Ă�ȂǁA�R����u���܂��B����ɑ��J�b�R�E���́A�h��̗��ɂ�������̗����Y��A�h���]������Ȃǂ��đ���ێ����悤�Ƃ��܂��B
���̂悤�ɁA������߂���W�͋��������܂���B |
| �Q�l�F�w�쒹���m����x |
|
|
|
|
|
|
�R�[�X�I�_�ŋL�O�B�e
���Ɍ�����̂����V�Q�� |
|
 |
| ���X�W�����q�g���c���̎����ɂ��� |
| ��1��ڂ̊ώ@�����ʎ����Ă����X�W�����q�g���̗c���̎����ɂ��āA���Ƃɗc���̎��̂͂��Ă�������Ƃ���A�G���g���t�@�[�K�Ƃ����u�a�ۂ����o����܂����B���̋ۂ̕����q���c���Ɋ��邱�Ƃɂ��A�̓��̐�����{�����D������A���Ɏ������ƍl�����܂��B�u�a�ۂ̐N���͂ƍ����̖h�q�͂Ƃ́A���x�⎼�x�Ȃǂ̊������ɂ���đ傫�����E�����Ƃ̂��ƂŁA��ʎ��̔w�i�ɂ́A�a�C���嗬�s����ɏ\���ȏ����������Ă����̂ł��傤�B |
| �Q�l�F�w�����P�����т̘b�x(������/���A�S���_�����狦��/���s�j |
|
|
|
|
|