■カヤツリグサ科観察のポイント
|
 |
|
 |
 |
 |
谷城勝弘先生
千葉県立佐原高等学校教諭。カヤツリグサ科植物をはじめヒルムシロ科、ホシクサ科などの水生・湿性植物を主な対象に分類学的研究を続けている。「カヤツリグサ科入門図鑑」を2007年に刊行。カヤツリグサ科植物の種間雑種に関する研究により日本植物分類学会学会賞を2013年に受賞した。 |
|
 |
●はじめに |
カヤツリグサの種名を調べるには、同定の決め手となる形質が掲載されている図鑑が必要です。「日本のスゲ/勝山輝男/文一総合出版」や自著で恐縮ですが「カヤツリグサ科入門図鑑/谷城勝弘/全国農村教育協会」がおすすめです。同定に必要な部位―鱗片や果胞、果実等の画像が掲載されているのが大きな特徴です。
植物の同定には花が決め手となりますが、カヤツリグサ科も同様です。しかし、カヤツリグサ科の花は花被片、いわゆる花びらが無く特殊な形をしているため、それら形質を表す用語を覚えなくてはなりません。難しそうに思われますが種ごとの形質がはっきりしていて変異も少ないので、見るポイントが分かれば同定しやすいと思います。
今回は、6種のカヤツリグサ科の標本を皆さんに用意しました。後ほど標本を見ながら各形質やどのようにみるのかなどを説明したいと思いますが、まず、カヤツリグサ科が生育している環境についてお話しいたします。 |
 |
 |
|
|
 |
1.場所のポイント |
| 身近な場所でいろいろな種類が観察できます。深い山奥や茂みのような場所の種類相はあまり豊富ではないので初めは避けたほうがいいと思います。開けた明るい場所が最適です。例えば以下のような場所があります。 |
|
|
 |
1) 休耕田
休耕後間もない場所が最適です。夏〜秋にカヤツリグサ属、ハリイ属、テンツキ属が多く生育します。アゼナ、キカシグサなどの一年生草本も同居していて観察の対象が多い場所です。年数を経た休耕田では遷移が進んでヨシやガマなどの大型多年草が侵入して種類相は衰退します。
畦に腰をおろしてゆったり観察することが、いろいろなものに気付くコツです。 |
 |
マガヤツリ、ハリイ、マツバイ、メアゼテンツキなどのカヤツリグサ科一年草が生える。
千葉県山武市2006.9.3。谷城勝弘撮影 |
|
|
|
 |
2) ため池
岸辺に注目です。夏〜秋に水位が低下して干上がった場所に、小型一年草のカヤツリグサ属が群生します。生活史がため池の水位変動に対応して維持されてきた特別な種類が多く含まれます。 |
 |
干上がった岸辺にアオガヤツリ、シロガヤツリ、ヒメアオガヤツリ、ニイガタガヤツリ、テンツキ、ヒメヒラテンツキ、トネテンツキなどが生育する。
千葉県いすみ市2008.10.18。谷城勝弘撮影 |
|
|
|
 |
3) 落葉広葉樹林
今日では山野の荒廃が著しいので、森林公園などをご利用ください。5月頃が適期です。アオスゲやメアオスゲのほか森林性のスゲ属が少なくとも2、3種類は観察できます。 |
 |
刈取りなどの人為的管理がある落葉樹林の林床にはシロイトスゲ、コイトスゲ、ヒカゲスゲ、ホソバヒカゲスゲなどのスゲ属が生育する。
千葉県多古町2006.4.22。谷城勝弘撮影 |
|
|
|
 |
4) 高層湿原
美しい景色の中で高山性のめずらしい種類が遊歩道沿いに現れます。種名の決定が難しい上級編です。 |
 |
遊歩道沿いの植物群。ワタスゲ、サギスゲと混生してカワズスゲなどがある。池内にはミヤマホタルイが生える。
福島県福島市吾妻山2005.8.4。谷城勝弘撮影 |
|
| この他、海辺の岩場のような潮風があたるような場所を好むカヤツリグサ科もいます。 |
 |
2.ホソガタホタルイ属とスゲ属の同定ポイント |
| さて、標本の出番です。今回は、ホソガタホタルイ属−ホタルイとイヌホタルイ、スゲ属−イソアオスゲとハマアオスゲ、センダイスゲ等について標本を使いながらお話ししたいと思います。 |
|
 |
1) ホタルイとイヌホタルイ―ホソガタホタルイ属
両者の外形はとてもよく似ていて、時には専門家でも混同することがあります。しかし、ホタルイは攪乱のない自然度の高い湿地に生え、イヌホタルイは攪乱地依存型です。ですから、水田地帯に生えるのは普通はイヌホタルイです。
ホタルイの小穂は卵形、イヌホタルイは長楕円形です。小穂とはカヤツリグサ科の花−小花という−の集まりで、1本の軸から複数の小花が出ている構造になっています。軸は短いので小穂はかたまりにみえます |
 |
ホタルイ。小穂は卵形で茎に2〜3個つく。茎は円柱形、断面は丸い。
千葉県多古町2003.9.23。谷城勝弘撮影 |
|
 |
 |
イヌホタルイ。小穂は狭い卵形。茎に4〜7個つく。茎は5〜6稜ある。
千葉県多古町2003.9.23。谷城勝弘撮影 |
|
|
また、茎(または桿)はホタルイは円柱形ですが、イヌホタルイには稜が5〜6稜あり少し角張っています。決定打は鱗片に包まれた果実です。(果実は楊子などを使って簡単に取り出せます。このとき刺針状花被片や雌しべも一緒についてきます。)鱗片とは、小花を構成する器官で、雌しべ、雄しべなどを保護するように小花の一番外側についています。また、刺針状花被片は、花弁の名残りだったと考えられる細長い片です。刺の有無、棘の向き等、属または種によっていろいろあります。
ホタルイの刺針状花被片は刺があり、果実とほぼ同長、イヌホタルイにも刺があり、果実より明らかに短くなっています。 |
 |
ホタルイの果実。果実表面は滑らか。刺針状花被片は果実とほぼ同長。柱頭は等しく3分岐する。
千葉県成田市2006.8.25。谷城勝弘撮影 |
|
 |
 |
イヌホタルイの果実。果実表面はやや皺状。刺針状花被片は果実より短い。柱頭は2分岐または1本が他より短い3分岐。
千葉県神崎町2006.9.2。谷城撮影 |
|
|
雌しべの先の柱頭にも注目です。ホタルイはそれぞれ同長の3岐、イヌホタルイは2岐か1本が他より短い3岐となっています。両者は種より下位の変種関係などに置かれることもありますが、生態的にも形態的にもこれほどの違いがあるので別種とみるのが適切でしょう。
さて、特徴的な立地環境ではこの2種が同居することもあります。そこではごく稀にではありますが、ホタルイモドキ
Schoenoplectiella ×juncohotarui が誕生することもあります。雑種は両種が生えていればどこにでも簡単に生まれるわけではありません。雑種の生育を許すいくつかの要因があると私は考えています。 |
|
 |
2) イソアオスゲとハマアオスゲ―スゲ属
海岸域に生える2種のスゲ属の紹介です。イソアオスゲはその名が示すように磯、ハマアオスゲは砂浜に生え生態が異なります。ハマアオスゲの方が全体に大型で頑丈な作りをしています。地下部はやや短く斜上する地下茎のあるのがイソアオスゲ、長く横走するのがハマアオスゲです。茎の先の穂は先端部が雄小穂(雄花の集まり)、下方には2〜4個の雌小穂(雌花の集まり)があります。
(カヤツリグサ科の小穂は、一つの小穂に雄小穂と雌小穂がある、雄小穂と雌小穂の二つがある、小花が両性花で雌雄期または雄雌期がある、など属や節によっていろいろなタイプがあります。) |
 |
イソアオスゲの穂。雄小穂は線形で細い。2〜3個の雌小穂は互いにやや離れてつく。ハマアオスゲの1/2程の大きさ。
千葉県一宮町2007.5.12。谷城勝弘撮影 |
|
 |
 |
ハマアオスゲの穂。雄小穂は棍棒状で太い。雌小穂は上方に集まる。
千葉県一宮町2007.5.13。谷城勝弘撮影 |
|
|
| ハマアオスゲの雄小穂は太く、雌小穂もその多くが雄小穂のある上方に集まっています。雌小穂の鱗片の内側には果胞という果実を包む袋状の構造があります。スゲ属ではこの果胞の形が種を見分ける重要な鍵です。表面に毛のあるもの、乳頭状突起をもつもの、上方の嘴とよばれるところが深く切れ込むもの、表面に何列かの筋のようなものをもつものなど種ごとに様々です。イソアオスゲとハマアオスゲの生育地の接点付近でイソハマアオスゲ
Carex ×bosoensis が発見できることもあります。 |
|
 |
3) センダイスゲ、センダイスゲモドキ、ナキリスゲ
スゲ属の多くは5〜6月に果期がありますが、ナキリスゲの仲間(ナキリスゲ節)は秋の9月下旬から10月頃です。スゲ属では地下部の様子が種を見分ける鍵の一つに使われます。基部の色や根茎の有無を調べるというものです。地上部だけでは正確な同定ができないのです。発達した長い地下茎のあるセンダイスゲ、その形質を少しもつセンダイスゲモドキの存在にも注意してみると観察の視点が広がります。 |
 |
センダイスゲモドキの基部、根茎。地下茎はやや這い、茎が疎らに出る。センダイスゲには長い地下茎があり、ナキリスゲは地下茎が発達せず叢生する。
千葉県君津市2005.10。谷城勝弘撮影 |
|
|
 |
| 今回は、ホソガタホタルイ属、スゲ属についてお話しいたしました。カヤツリグサ科には他にハリイ属、カヤツリグサ属、テンツキ属、クロアブラガヤ属、シンジュガヤ属、ヒメクグ属、ウキヤガラ属など一味ちがう仲間が多数含まれます。これらもおもしろいグループなのでまたの機会に紹介したいと思います。 |
 |
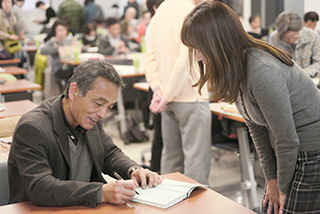 |
「カヤツリグサ科入門図鑑」にサイン中の谷城先生。
事務局撮影。 |
|
 |
| アンケートには「実際に観察を始めたら難しいのだと思いますが、谷城先生のお話をきいてカヤツリグサ科の同定を私にもできそうに思いました」といった感想もありました。ぜひカヤツリグサ科を楽しんでくださいね。 |