■毒虫の注意(山崎先生)
 |
| ※開催前に、この時期に遭遇しやすい危険な虫たちについての解説と注意喚起が行われました。 |
 |

|
 |
危害を受ける昆虫とひとくくりにされている虫たちには、大きく分けて2種類あります。「こちらの不注意で危害にあってしまうもの」と「向こうから危害を加えて来るもの」です。
このうち後者は我々の血液をもとめて飛来するカ・アブといった吸血昆虫たちで、虫よけグッズなどでその被害を減らすことができます。この観察会では携帯式蚊取り線香の使用は禁止なので、基本的にはスプレーの使用をお勧めします。
|
|
 |
とくに注意をお願いしたいのは前者のタイプの害虫です。ひとつには、今日の観察ポイントにも生息していますが、イラガやドクガといったケムシ類が挙げられます。イラガは幼虫の時期に毒のとげをもち、刺さるとかなり強い痛みを感じます。ドクガは幼虫のみならず、一生を通して毒をもち、さわるとかぶれて強いかゆみを感じます。街路樹の葉の裏などに多く生息していますので、注意して歩くようにして下さい。
またスズメバチやアシナガバチといった毒針をもつハチ類などもこちらのタイプにあたります。彼らの被害にあうのは、とくに巣に近づきすぎてしまった場合が多いです。こちらが気付かないうちに接近してしまい、襲われることもあります。注意としては飛来するハチの数が多くなったら気を付けること、そして巣の入り口をふさがないようにすること、などがあります。(脇本)
|
|
|
 |
|
■オッタチカタバミの種子散布(植物)
 |
 |
| 果実がはじけるようすを実際に触って観察する |
|
 |
カタバミやその仲間のオッタチカタバミは、身近にどこでも見られますね。
熟した果実にさわると、中からたねを飛ばして、手にピンピンと当たります。
さやが裂けて種子をはじき飛ばす、といったことは、図鑑に書いてありますし、みなさんも知っているのではないかと思います。
よく観察すると、たねを飛ばすのには秘密があることがわかりました。
果実のさやを見ると、白い半透明のものが残っているのが見られますね。この白いのがたねを飛ばしているのです。 |
|
 |
|
|
| オッタチカタバミの果実(左)と拡大写真(右)。白い半透明のものが仮種皮 |
|
 |
この白いものの正体はよくわからないのですが、仮種皮(かりしゅひ)ではないかと思われます。
裂け目から見えるたねは、まだ仮種皮に包まれています。十分に熟すとこの仮種皮が“クリンッ”と反転してその勢いで中のたねが飛び出す仕掛けになっています。このとき、仮種皮も飛んでしまうことが多いようですが、写真のようにさやについて残るものもあります。 |
|
 |
| 今回はオッタチカタバミで観察しましたが、カタバミの種子散布も同じです。 |
 |
これらのことがわかってからいろいろな本を見ると、中にはこのことが書いてあるものもありました。
見る人は見ているんですね。私たちは今までは読み飛ばしてしまっていたようです。(大野)
|
| |
|
|
■ツユクサの花、再発見(植物)
 |
| ツユクサは色々なところで見られますが、花の中をよく見たことがありますか? 一つだけ失敬して、観察してみましょう。 |
 |
 |
| ツユクサの雄しべと雌しべ |
|
 |
| 大きな花弁が2つありますが、それ以外に1枚、白い小さな花弁がついています。がくと同じような花弁です。 |
 |
長く突き出ているのが3本ありますが、2本の雄しべと、1本の雌しべです。
雄しべはあと4本あって、中くらいの長さのものと、短い3本です。これらは仮雄しべで本来の機能を持たないものだと言われていますが、どうやらそうでもないようです。 |
|
|
 |
総苞をめくってみましょう。
開いている花の先につぼみがあって、元の苞には果実があります。
総苞の中は複数の花がある花序であることがわかります。 |
 |
右端に枝状のものが出ていますが、これは何でしょうか。
これは本来の主軸の残ったものだと考えられています。
普通、ここには花をつかないとされていますが、気を付けて観察してみるとそうでもないことがわかりました。 |
|
 |
 |
| 1つの花序に2つ同時に咲くこともある |
|
 |
| 周りを見ると、2つの花を同時に咲かせているものもありますね。これらは主軸にも花をつけたもので、2個咲きのツユクサは意外にたくさんあります。 |
 |
| 2個咲きのうち、主軸の花(上の花)は雄花だという人もいるようですが、私たちの観察では上の花も雄しべのある両性花であることも普通に見られました。 |
|
|
 |
もう一つ面白いことがあります。
ツユクサは3回受粉します。
1、開きかけの時に自家受粉
2、花が開いているときに虫媒受粉
3、花が終わったときに自家受粉
の3回です。 |
 |
| 受粉のために、あの手この手と工夫しているようです。(西田)
|
|
 |
|
|
| 咲き終わった花(左)と、その花弁とがくを外した状態(右) |
|
|
|
 |
|
|
 ページトップに戻る↑
ページトップに戻る↑ |
■ハスモンヨトウ・セスジススメとイラガ(平井先生)
 |
|
|
 |
サトイモの大きな葉が茂っています。すこし虫食いがありますが、その横にいるイモムシが見えますか?
これはハスモンヨトウというガの幼虫で、非常に多くの植物を食害する極めて重要な農業害虫です。成虫は前翅にはっきりとした斜めの線が入るため、「斜紋(はすもん)」という名がつけられました。
ハスモンヨトウは本来南方系の昆虫で、毎年この近辺でも観察されますが、越冬はできずに死滅してしまっていると思われます。越冬ができるのは、年間最低気温が-3.5℃までの地域である「本州南岸線」までであると考えられています。 |
 |
| 約2m先方の葉上に、ハスモンヨトウの中齢幼虫と並んで黒っぽいイモムシが見えます。これは日本全国に生息するスズメガ科のセスジスズメの幼虫です。成虫は夜間に飛び回り葉上に産卵します。幼虫はサトイモのほか、サツマイモ、ノブドウなどの葉を食べます。サトイモやサツマイモの葉に大発生したときには防除が必要になります。 |
|
 |
さて、すぐ先のカキの木の下を通るときは注意して下さい。この葉の裏には、ヒロヘリアオイラガの幼虫が生息しています。
この仲間の幼虫には似たものがあり、背中の中心(背中線)で見分けられます。カキにも多いですが、幅広い樹木を食害する広食性の昆虫です。
幼虫にはとげが密生しており、刺されるとしびれるようなショックと痛みを感じます。
(脇本)
|
 |
 |
| ヒロヘリアオイラガ幼虫 |
|
|
|
 |
|
■アカトンボの話(鈴木先生)
 |
 |
| 連結して飛行するアカトンボ(田仲義弘) |
|
 |
この時期、多くのアカトンボが飛んでいるのを観察することができます。アカトンボという呼び方はアカネの仲間の総称として使われており、ナツアカネ、アキアカネ、ノシメトンボなどが含まれています。
水辺で観察していると、それぞれのトンボの連結・交尾・産卵のシーンを観察することができます。交尾の際、雄が腹部後端の把握器で雌の頭部をつかみ、雌は雄の胸部にある貯精嚢に腹部の後端を押し付け、精子を受け取り、受精させます。シオカラトンボやオニヤンマなどは交尾後、連結は解消されて雌が単独で産卵しますが、アカネの仲間は一部の種を除いて、交尾の後も連結した状態で飛行します。
|
|
 |
|
その後は産卵となるのですが、種によって産卵スタイルが異なります。アキアカネは産卵の際、雌が腹部後端を水面にたたきつける「打水産卵」を行うのに対して、ナツアカネやノシメトンボは、空中を飛びながら水面に卵を落とす「打空産卵」を行います。田仲先生が撮影されたこちらの写真では、アキアカネの打水産卵のとき、飛び散った水滴の中に産み落とされた卵が入っているのが確認できます。(脇本)
|
 |
 |
| 打水産卵のようす(田仲義弘) |
|
|
|
 ページトップに戻る↑
ページトップに戻る↑ |
|
■コゲラの巣(唐沢先生)
 |
 |
| コゲラの巣穴 |
|
 |
| 下見の時にキツツキがつついた穴をみつけました。キツツキの仲間はくちばしで木を削って穴をあけ、子育てやねぐらに使います。 |
 |
さて、この穴がある枯木はなんの木でしょう?
隣の木と木肌が似ていますね。これはどうやらアカメガシワでしょう。 |
 |
キツツキの仲間には、コゲラ、アカゲラ、アオゲラ、クマゲラなどがいます。それぞれ体長が違うので、作る巣穴の大きさによって、どの種が開けたものなのかを見分けることができます。巣穴の口径を計ってみましょう。
縦・横はそれぞれ約40mmありました。コゲラが35mm、アカゲラが44mm、アオゲラが50mm、クマゲラは120mmほどの巣穴を開けるので、これはコゲラのものだと考えられます。 |
 |
| コゲラは、小さくて力が弱いので枯れ木に巣穴を開けることが多いです。他のアカゲラ、アオゲラ、クマゲラは生木に開けることも多いです。 |
|
|
 |
| ※ここで「ギィ」という鳴き声が。 |
 |
| どうやらコゲラが近くにいますね。「ギィ」という鳴き声は仲間同士のコミュニケーションをとっている声です。 |
 |
| ※今度は「キョキョ」と鳴く声。 |
 |
これは、警戒している声ですね。
我々が巣穴の近くに居ることに警戒しているのでしょう。(深澤)
|
|

|
|
■鳥が作った森?(中安先生)
 |
 |
| 鳥による被食散布でできたと考えられる森 |
|
 |
コゲラがつついた枯れ木の周辺を見渡すと、アカメガシワ、イイギリ、ケヤキ、エノキ、ムクノキ、ミズキ等の木が生えています。それぞれ、赤やオレンジ、まだ熟していない緑の実がついていますね。
さて、今度は地面に落ちている実を拾って見てみてください。この赤い実はイイギリですが、よく見ると表面にV字の形をつけた実が見つかります。これはくちばしで挟んだ痕で、鳥が飲み込もうとしてうっかり落としてしまったのだと思われます。 |
|
 |
さて、植物たちは子孫を残すために、様々な手段を用います。その中で、鳥や動物に果実(種子)を食べてもらい散布する方法を被食散布といいます。エノキ、アカメガシワ、ムクノキ、ミズキ等がそうですね。
他には、風によって散布する方法があり、これを風散布と言います。ここのエリアでは、ケヤキがそれに当たります。
また、重力によって散布する方法もあり、これを重力散布といいます。熟した果実や種子が地面に落下するということです。アカメガシワは被食散布と重力散布のどちらも利用しているようです。 |
 |
| この森では被食散布で殖える樹種が大半を占めており、「鳥がつくった森」と言えそうですね。(深澤)
|
|
|

|
|
■帰化植物とアレチウリの巻きひげ(植物)
 |
| ※芝川の橋を渡ったところで川の土手の植物を観察しました。
|
 |
ここは帰化植物が多いです。
秋の花粉症を引き起こすオオブタクサ、アレチウリ、コセンダングサ、セイバンモロコシ、オオオナモミなどが生えています。
帰化植物は、ヒトの手が入ると真っ先に出てきます。そして何年かすると在来種が入ってきて安定してくるようです。
この土手に広くはびこっている、果実にとげのあるつる植物がアレチウリです。近年急激に増えた雑草で、各地で問題となっています。
|
 |
 |
| 帰化植物の繁茂する芝川の土手 |
|
 |
 |
| 指で触れるとすぐに巻きつき始めるアレチウリの巻きひげ |
|
|
|
 |
このアレチウリは巻きひげで他のものにつかまって成長します。
まだ巻き付いていない巻きひげの先端をやさしくなでるとどうなるでしょう。
|
 |
| ※試していた参加者から歓声が上がる |
 |
| 手に巻き付いてきましたね。一度巻きはじめるともう止まりません。反対側をなでても反応しません。 |
 |
| 巻きひげは、先端が絡みつくとばね状に巻いていきます。そのため真ん中に向きの変わるところがあります。(西田)
|
|
 |
 |
| アレチウリの巻きつき方 |
| 「雑草博士入門」(全農教)より |
|
|
|
|

|
|
■ジョロウグモの話(浅間先生)
 |
ジョロウグモは秋を代表するクモです。
ここにはたくさんの網が張られていますね。 |
 |
 |
目が細かいジョロウグモの網
ぎざぎざしているのが足場糸 |
|
 |
大きいのが雌で、普通1頭の雌に対して複数の雄がいます。みんな交接のチャンスを狙っており、雄同士で戦いが起こることもあります。結果として、雌の一番近くにいるものが強い雄ということになります。
餌を食べるときなど、雌がスキを見せた時に交接します。 |
 |
雌はあと1か月ほどたつと(9月末から10月はじめ)産卵します。そして冬になる前に死んでしまいます。
さて、ジョロウグモの網の特徴、つまりほかのクモと違うところはどこでしょう。 |
 |
1. 網が大きくて目が細かい。しかも何重にもなっている。
2. ぎざぎざの足場糸が残って、五線譜のように見える。
3. 縦糸がほかのクモよりも2倍くらい多い。 |
 |
| 雨が降った後は粘性が低下するので、網を張りなおす必要がありますが、このときジョロウグモは半分だけ張り替えます。大きくて目が細かいから省力化するんですね。 |
|
|
 |
| クモの網をよく見てもらうと、いろいろなことがわかります。 |
 |
| 2. の足場糸はギザギザになっているところです。 |
 |
| ほかのクモは足場糸を回収してしまうので、このギザギザはジョロウグモの網の特徴です。 |
 |
| それから、3. の縦糸は、途中で二またに分かれているところがあります。もともと二本が合わさって一本の糸になっていますが、ときどき足でたたいて二本に分けるようです。 |
  |
| 大きなクモ網は風で揺れるのでわかりにくいですが、いろんなことがわかりますね。(大野)
|
|
 |
 |
| ぎざぎざしているのが足場糸 |
|
|
|

|
|
|
本年度の見沼田んぼでの観察会は今回で終了です。
参加していただいた皆さん、講師の皆さん、本当にありがとうございました。
野外観察会の皆勤賞のしるしでもある修了証ですが、今年は19名の方にお渡しすることができました。 |
 |
 |
| 観察会修了後、唐沢学長より修了証が授与されました |
|
 |
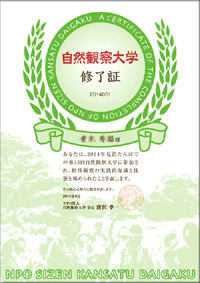 |
| 本年度の修了証 |
|
|
 |
| ●終了後のうれしい話 |
 |
観察会終了後に、親子で参加してくれている赤田さんが、夏休みの自由研究で提出した「見沼のつる植物たち」を紹介してくれました。
いろんなつる植物を詳しく観察し標本を添えた、恵理さん(小学6年)の力作です。 |
 |
観客の講師陣からは拍手喝采が起こりました。
このようなうれしいことがあると、講師やスタッフには何よりの励みになります。
恵理さん、ありがとうございました。そして大きなものを大事に抱えて参加してくれたお父さん、ありがとうございました。 |
|
 |
 |
|
|
|
 |
| (レポートまとめ 自然観察大学事務局 脇本哲朗)
|
|