| 2003年 |
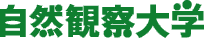 |
第2回
(その3) |
|
|
|
| 湿原のあちこちに葉先がクルリと巻いているヨシが見られます。これはフクログモ科の巣ですが、ヤマトコマチグモとカバキコマチグモの場合が多いようです。両種ともススキの葉を曲げて住居を作ることが知られていますが、ここではヨシを利用しています。クモは用途によっていくつかの巣を作りますが、この巣は交接と育児のためのものです。ヤマトコマキグモとカバキコマチグモは姿ばかりでなく巣までよく似ています。後日、講師の浅間茂先生にヤマトコマチグモであることを確認していただきました。ヤマトコマチグモとカバキコマチグモでは交接用の巣は同じ形ですが、産卵用の巣はカバキコマチグモのそれは少しクルクルとした形になります。ススキでもヨシでも葉が丸まっていたら開けたくなるかもしれません。しかし、いったん開けられた巣は隙間からアリなどの天敵が入り込み中の幼虫が捕食されてしまいます。また、カバキコマチグモは毒を持ち、攻撃性があり、咬まれる危険性があります。むやみに開けないようにしてください。 |
 |
| ヨシにできたヤマトコマチグモの巣(浅間原図) |
|
|
 |
|
|
|
湿原の中に白いものが目立つ一角がありました。ハンゲショウの白い葉と、ドクダミの白い総苞片です。中安均先生によると、これらは虫を呼ぶための看板のようなものと考えられるとのことです。中安・浅間先生による「校庭の生き物ウォッチング」ではドクダミの花が紹介されています。
ハンゲショウとは「半夏生」と書き、夏至から11日目の7月2日頃の季節を指すそうです。この頃、茎上部から1〜2枚目の葉が白くなることからこんな粋な名前が付けられたのだそうです。あるいは半化粧からきたという節もあります。一方、ドクダミは生育が旺盛で特異な匂いを発し、胃腸病の薬草として知られています。両種ともドクダミ科の植物です。
ドクダミ科の植物は被子植物のなかでも古い植物のグループで、花には花弁やがくがありません。代わりに花序の基部の葉や総苞片が目立つようになったと考えられます。よく目立つ花弁を備えた虫媒花の進化を考える上でも興味深い観察対象でしょう。 |
|
|
| ハンゲショウ(左)。ドクダミ(右)(「校庭の生き物ウォッチング」より) |
|
|
 |
|
|
|
| 木道脇の湿原にコウガイビルを見つけました。湿気を好み、雨の観察会にふさわしい生き物です。扁形動物門に属します。写真のようにあまり姿のいいものではなく、ヒルという名前からも吸血性の危険な生き物を連想させますが、吸血することはありません。コウガイビルの仲間はカタツムリの天敵として知られています。また、口と排出口が一つで体の中心にあります。石をひっくり返して調べると案外見つかるかもしれません。 |
 |
| クロコウガイビル(浅間原図) |
|
|
 |
|
|
|
観察の途中でヒルガオが回覧されました。よく見ると、ヒルガオの花の内側に小さな黒い虫がいます。ルーペでアップにすると翅が総(ふさ)状の虫で、アザミウマの仲間です。姿が小さく、植物から汁を吸って生活していますが、吸汁跡が斑点などとなります。斑点状の吸汁跡をつけるアザミウマは農業上の重要な害虫になりますが、その多くがThripsという属に属することから、スリップスとも呼ばれます。菌食性や肉食性の仲間もいます。
アザミウマという不思議な名前のいわれが、「農作物のアザミウマ」にありましたのでここに紹介します。明治の時代、大阪辺りでは子供たちが、アザミの花を「ウマ出よ!ウシ出よ!」といいながら、手の上で軽くたたき、落ちてきた虫の数を競って遊んだことがあるそうです。ここでいうウマやウシは、他の地方でもあるように昆虫をさしていたようで、この時潜んでいた小虫がアザミウマの類だったとのことです。 |
 |
| ヒルガオで見つけたアザミウマ |
|
|
 |
|
|
|
| 湿原ではガマが目立ってきました。ガマは特徴的な穂を付けます。雄花から黄色い花粉が出てきます。岩瀬徹学長から、この穂にある花粉には止血効果があることが紹介されました。「因幡の白兎」ではワニに襲われ、血まみれになったウサギが、ガマの穂に包まれて救われるシーンがありますが、当時から、ガマの花粉が薬として利用されていたということでしょうか。 |
 |
| ガマの穂 |
|
|
 |
|
|
|
左の写真は前回の観察会で紹介のあった、コゲラの開けた穴です。観察会の最後に、池のほとりで唐沢孝一副学長から紹介のあったものです。春先にコゲラが穴を開けていたのですが途中で放棄したとのことでした。右は観察会のコースに入っていませんが、台地の上で見つけたコゲラの穴です。よく見比べてください。池のほとりの穴は、見て分かるように中まで穴が開けられていますが、台地の穴は浅くしか開いていません。コゲラはクモと同様に穴をさまざまに利用しますが、池のほとりの穴は育児などの巣のためのものであり、台地の穴は樹の幹にいる虫を食べた跡です。
コゲラは最近都市部でよく見られ、枯れた樹を利用して穴を開けることが知られています。 |
|
|
|
 |
|
第2回の観察会を3回に分けて紹介してきました。こうやって並べてみると多くの生き物と出会っていることになります。第3回観察会は10月4日(土曜日)です。第2回と季節が大きく変わっています。どんな生き物が現れるのでしょうか。
昼食後に撮影した写真を最後に第2回のルポを終了します。 |
 |
|
|
|
| 樹のうろに造られていたニホンミツバチの巣を撮影したものです。ニホンミツバチが飛び交う中をこわごわと撮影したのですが、偶然に巣盤が写っていました。ミツバチの仲間は、アシナガバチやスズメバチと違い、縦に巣盤を造ります。ミツバチは蜜のある花の位置を8の字ダンスで知らせることがよく知られていますが、これは縦の巣盤では方向を指示できないために発達したのだと、田仲義弘先生から説明がありました。 |
 |
| ニホンミツバチの巣盤 |
|
|
 |
|
|
|
| イロハカエデ(イロハモミジ):カエデ科。落葉樹。林内や林縁、谷あいに普通に見られる。秋の紅葉を代表し、庭園木としても利用され、多くの園芸品種がある。幹は直立する。高さ10〜15mと大きくなり、上部が広がる。幹には縦の細かい裂け目があり、枝は平滑で緑色、葉は葉は大きく裂け独特の形をする。花期は4〜5月、新しい枝に新葉が出るころ、長い柄をもった花をつける。(「校庭の樹木」より) |
 |
| 紅葉した樹形 |
|
 |
| 長い柄の先に花をつける |
|
 |
| イロハカエデの樹皮 |
|
|
|
 |
| ムラサキシキブ:クマツヅラ科。山地の疎林や森林地帯の林床、造林地に生息する。高さ2〜5m。幹はよく分枝し、葉を密生させる。葉は対生し、基部が狭くなっている。6〜7月、淡紫色の筒状花を集散状につけ、秋には紅紫色した球形の果実ができる。(「日本原色雑草図鑑」より) |
 |
| ムラサキシキブの枝 |
|
 |
| 葉は細く対生する |
|
 |
| 秋に赤い実をつける |
|
|
|
 |
| ツリバナ:ニシキギ科。落葉樹。林内や林縁に生息する。幹は直立し、樹皮は灰色でやや粗い。高さ2〜5mで斜面林の低層を形成する。葉は対生し、内側に曲がった鋸歯をもつ。花期は6〜7月で類白色の小さな花をつける。秋には丸い果実を付け、熟すと赤く色づく。花や果実を下垂してつけるところからこの名がある。(「日本山野草・樹木生態図鑑」より) |
 |
| 紅葉が始まったツリバナ |
|
 |
| ツリバナの果実 |
|
 |
| 灰色の樹皮 |
|
|
|
|
|
|
|
|